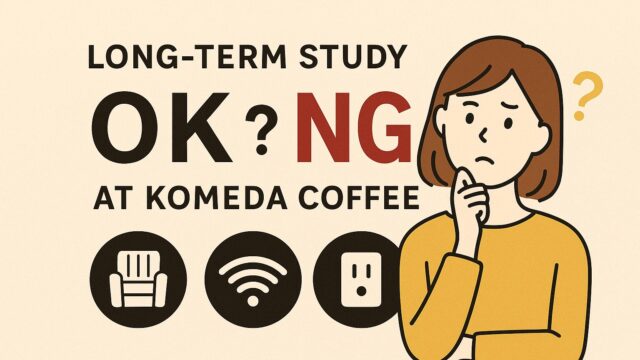旅行や参拝の記念に購入した「お守りキーホルダー」。バッグや財布につけて持ち歩いているうちに色あせたり、鈴や金具が外れてしまったりして「そろそろ手放した方がいいのかな」と思う瞬間がありますよね。
ただ、いざ処分しようとすると――
-
「プラスチックや金具がついているけど、燃えるごみに出して大丈夫?」
-
「購入した神社じゃなくても返納できるの?」
と迷ってしまう人は多いはずです。
実は、お守りキーホルダーの処分にはいくつかの方法があり、きちんとした手順を踏めば心配はいりません。寺社に返すのが一般的ですが、遠方なら郵送、地域のどんど焼き、自宅での清めなど選択肢は複数あります。
この記事では、5つの処分方法を詳しく紹介し、それぞれの注意点や手順を分かりやすく解説します。大切なのは「これまで守ってくれてありがとう」という感謝の気持ちを込めること。処分方法を知っておけば、安心してお守りを手放すことができます。
1.購入した神社・お寺に返納する
最も基本となるのが「授与してもらった場所へ返す」方法です。
多くの神社やお寺では、正月の時期に「古神札納所」「古いお守り納め所」といった返納箱が設置され、そこにお守りやお札を納めることができます。キーホルダー型でも問題ありません。特に新年はお守りの役割を一区切りさせる時期とされるため、前年にいただいたものを感謝を込めて返納すると良いでしょう。返納には明確な料金は不要ですが、お礼の意味を込めてお賽銭を添えるのが一般的です。ただし、寺社によっては正月を過ぎると回収を行わない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
2.遠方の場合は郵送で返納する
旅行先で受け取ったものや、人から贈られた場合など「直接返しに行けない」ケースもあります。そのとき便利なのが郵送での返納です。
郵送の流れ
-
公式サイトや電話で郵送対応を確認する
-
半紙で包むか封筒に入れる(丁寧に扱いたい場合は半紙がおすすめ)
-
封筒の表に「お守り在中」「お焚き上げ依頼」と朱書きする
郵送を受け付けていない寺社もあるので、必ず確認をしてから送りましょう。
「ちょっと手間がかかるな…」という場合は、次に紹介する方法を検討してみてください。
3.別の寺社にお願いする
購入した寺社が遠すぎたり、返納を受け付けていなかったりする場合は、近隣の寺社にお願いすることも可能です。
ただし、いくつか注意点があります。
-
神社のお守りは神社へ、お寺のお守りはお寺へ
-
お寺は宗派があるため、同じ宗派での返納が望ましい
-
キーホルダー型は素材によって断られることがある
勝手に置いて帰るようなことは厳禁。必ず事前に問い合わせて、受け付け可能かを確認することが大切です。
4.地域のどんど焼きで処分する
「どんど焼き」とは、毎年1月15日前後の「小正月」に行われる火祭りの行事で、お正月飾りや古いお守りを炎で焚き上げて浄化する伝統行事です。地域によって「左義長(さぎちょう)」や「さいと焼き」と呼ばれることもあります。どんど焼きの起源は平安時代までさかのぼるといわれ、宮中で正月に用いた飾りや書き初めを焼いて、その火で無病息災や立身出世を祈ったことが始まりとされています。やがて全国に広がり、現在でも地域ごとに形を変えて受け継がれている行事です。
どんど焼きで行われること
-
地域の住民が門松やしめ縄、書き初めなどを持ち寄る
-
わらや竹でやぐらを組み、その中に飾りを入れて火を点ける
-
燃やした炎や煙にあたると「一年間健康に過ごせる」とされる
-
書き初めを炎にくべると「字が上達する」ともいわれている
火は「神聖な浄化の力」を持つとされ、炎に包まれることでお守りの役割を終え、感謝とともに天に帰るという意味があります。
お守りキーホルダーを出すときの注意点
ただし、どんど焼きは基本的に「燃やせるもの」が対象です。プラスチックや金具、パワーストーンなどのパーツはそのままでは受け付けてもらえないことが多いので、事前に取り外しましょう。燃やせる部分(紙・布など)のみを持ち込むのがマナーです。地域によっては「お守り類は受け付けない」「神社で授かったものだけ」とルールが決まっている場合もあるため、開催を確認する際にあわせて問い合わせておくと安心です。
子どもと一緒に参加する楽しみ
どんど焼きでは、火にあたったり、焼いた団子や餅を食べると「病気をしない」「健康で過ごせる」と信じられてきました。子どもと一緒に参加すれば、地域の文化を体験できる良い機会にもなります。大きな炎を見上げる迫力は、大人にとっても印象に残るものです。
5.自宅で清めて処分する
寺社に持って行けない、どんど焼きも難しい。そんなときは自宅でお清めをしてから処分する方法があります。
自宅での清め方
-
燃やせない部品(金具・プラスチック・石など)を取り外す
-
半紙の上に並べ、両手を合わせて感謝の言葉を伝える
-
天然塩をひとつまみ振りかけて清める
半紙と天然塩には古来より浄化の力があるとされ、お清めには欠かせません。清めた後は、自治体のルールに従って可燃ごみや不燃ごみに分別しましょう。お清めをしっかり行っていれば、一般のゴミと一緒に処分しても問題ありません。大切なのは「きちんと感謝を伝えてから処分する」ことなのです。
お守りは処分しなくてもよい?
「お守りは1年経ったら処分しなければならない」とよく言われますが、必ずしもそうではありません。一般的には1年で新しいものと交換するのが望ましいとされますが、安産祈願や合格祈願などは願いが叶った時点で返すのが目安とされています。一方で、大切な思い出が詰まったものや、手元に置いておきたいものは無理に処分しなくても構いません。参拝の際に「今まで守ってくださりありがとうございます」と感謝を伝えるだけでも十分です。
まとめ|感謝の気持ちを忘れずに処分を
お守りキーホルダーを処分する方法は、大きく分けて5つあります。
-
購入した神社・お寺に返納する
-
遠方の場合は郵送で返納する
-
近隣の神社やお寺にお願いする
-
地域のどんど焼きで焚き上げてもらう
-
自宅で清めて処分する
どの方法を選んでも共通して大切なのは、ただ「捨てる」のではなく、これまで自分を守ってくれた存在に感謝を込めて手放すことです。お守りには「願いを込めた瞬間から守ってくれる」という意味があるため、処分の仕方に迷っていても、感謝を忘れなければバチが当たることはありません。特にキーホルダー型のお守りは金具やプラスチックなどが含まれるため、少し工夫が必要ですが、手順を踏めば問題なく処分できます。
また「必ず1年で処分しなくてはいけない」という決まりはなく、思い入れがあれば大切に手元に残しても構いません。願いが叶ったときや、新しい一年を迎えるときに区切りとして手放す人が多い、という程度の目安です。
もし「どうすればいいか分からない」と迷ったら――
-
まずは購入した寺社に問い合わせてみる
-
それが難しければ地域のどんど焼きを調べる
-
それでもダメなら自宅で清めて処分する
この流れで考えれば安心です。
お守りはただの物ではなく、あなたや家族を守るために寄り添ってきた存在です。だからこそ、最後まで丁寧に扱うことが、心を整えることにもつながります。「ありがとう」の気持ちを込めて手放す――それこそが、お守りにとって最も正しい処分の仕方だといえるでしょう。